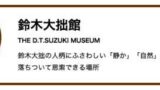本ブログは観光業、企業接待、留学生対応等で英語案内が必要ながら、多忙で準備に時間をかけられない方々の為にすぐに使える情報を分かりやすく解説しています。今回は『どうする英語案内?AIを超える為の情報支援』シリーズの《鈴木大拙館》編です。
0- 基本的な考え方(前書き)
本シリーズでは《鈴木大拙館》に関する代表的な情報サイトを(A)目的と(B)カバー範囲に照らして下記の5領域『政府(①国外展開、②国内展開)系、③自治体・公益系、④協業(専業者)系、⑤独立系』に分けて(一例として)ご紹介しています。この(A)(B)視点により現場の皆様が自ら日々検索される膨大な情報に(AIにはできない)より深堀した判断が加えられます。👉5領域分類の背景についてご参照の際は《Info@ブログついて》へ。
1.政府(海外展開)系
ここで引用したサイトは(A)目的を国際競争、(B)カバー範囲を世界規模として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。
Travel Japan(JINTO:日本政府観光局)【多言語】
ここでは、全世界に対し政府がどの様な内容、表現でPRして関心を高めようとしているかチェックできます。最近はあまり生成Aiに引用されていない感じですが、いつも通り今回テーマの’don’t miss’をチェックします。多くのテーマは3点ですが、ここでは2点(いつもの建築アイテムで)インバウンドの興味傾向を反映しています。日英きっちり対訳されてますが、全般的に日本語は自動翻訳の影響と思われる不自然な言い回しが多いのですが、《鈴木大拙館》については問題ないようです。基本的に観光業、個人旅行者はこれを知っていると想定して、またこれをベースに実際の案内時は相手に合った修正をします。👉下記引用は’鈴木大拙館(日本語)’からです。
Japan Guide【英】
正式な政府機関ではありませんが政府認定資格のVisit Japan 大使が設立した訪日観光情報サイトとして、海外発信力の強さから、本ブログではこのグループに置いています。海外の利用度が高い点で、公的なJINTOと内容、表現を比較する事が有用です。利用数の多さを反映してか(R5年現在)AIもこのネタを本サイトからよく引用しているようです。特に欧米系の利用者が多いと言われ、実務的な誘導も意識されていて、英語系インバウンドのニーズチェックに有効です。《鈴木大拙館》は公式サイトがありますので、詳細情報は通常はそこにお任せが多いのですが、この公式サイトは言葉少なめがウリなので、(それが直接どれほど影響しているか断言できませんが)ここでは結構量があります。👉下記引用は’D.T. Suzuki Museum’からです。
2.政府(国内展開)系
ここで引用したサイトは(A)目的は国内活性、(B)カバー範囲は国内規模として発信内容(表現)も発信量もそれを反映しています。
全国観光資源台帳(日本交通公社)【日】
公益財団法人日本交通公社が(JTB分離後、研究的機能を持つようになり)このサイトをサポートしています。個人的には観光庁の多言語データベースが長い間更新されていない(2011年オーブンの当館も当然未カバー)ので(公的機能として)こちらに(観光検索ツールとしても整備され)シフトして来ている印象ですが、前者の観光業での英語表現指導のような役割は当然なく、(R5現在)英語サイトもないようです。特段インバウンドを意識した表現もなく、データベースとしての客観的な内容チェックに有用です。👉下記引用は’鈴木大拙館’(日本語)からです。
3:自治体/公益(地元振興)系
ここで引用したサイトは(A)目的は地域活性、(B)カバー範囲は自治体規模として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。一般的傾向として生成AIはこのグループからの引用が多いので、基本的事項を押さえるには無難ですが、一般的なインバウンドには当然十分ではありません。
鈴木大拙館《公式》【日英】
金沢文化振興財団による公式サイトなので、通常はこれでかなりカバーできるはずですが、彼の最大の功績は思想の伝導なので、この様に(目に見える)成果物による展示説明の少ないサイトになるのでしょう。当然、ここに限らず、インバウンドにご満足頂ける案内説明のための背景情報は他でもカバーしなければなりませんが、《鈴木大拙館》はそのウエイトが高くなりそうです。ある意味、有名な禅寺にご案内するのに似ているかもしれませんが、この館に彼が住んで修業していたわけでもなく、彼が造った庭が残っているわけでもなく、その意味では禅寺説明より難しいとも言えるでしょう。鈴木大拙ファンであれば、そのイメージの空間や池を楽しめるでしょうけど、彼の著名さにだけ惹かれて訪問したお相手には、それなりにわかり易いエピソード(本ブログでの他引用サイトにある裏話や書籍サイトにある海外で評判の問答例など)を準備されることをオススメします。👉下記引用は日本語ポータルから。
金沢市(Pick Up 鈴木大拙館)
主要な金沢観光スポットの情報チェックでは外せない[金沢旅物語]や他の地元有力サイトも、殆ど中身のない紹介ばかりの中、逆に普段は無難な紹介が多い金沢市の今回サイトは、(英語の記載としてはありませんが)英語案内の裏話ネタにおススメです。👉下記引用は同サイトから。
4.協業(専業者展開)系
ここで引用したサイトは(A)目的は直接収益、(B)カバー範囲は地場産業として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。直接的にインバウンドからマネタイズするビジネスモデルと言えます。
文化の森【多言語】
そもそも《鈴木大拙館》は利潤優先の民間運営ではないので、本グループは殆どないのですが、金沢文化振興財団が関わる〈文化の森!お出かけバス〉だけ引用しておきます。案内説明自体に役立つコンテンツはありませんが、《鈴木大拙館》の経済的立ち位置の体感に役立てばと思います。👉下記は日本語サイトからです。多言語もありますがリンクが上手く繋がりませんため。
5:独立(テーマ別)系
ここで引用したサイトは(A)目的は間接収益、(B)カバー範囲はイベント&プロモーションとして置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。上記4系統以外では得られない、独自ノウハウや経験をベースに個性的に展開されているサイト数多(旅行事業、地元個人ベースサイト等)ありますが、冒頭の主旨からも、ここでは細かな引用は控えます。(観光業に係る皆様はもちろんこのグループはよく熟知されてますので)代表例として下記ご紹介させて頂きます。
(Wikipedia)鈴木大拙館
マネーとしての間接的な収益を得ているサイト(組織)ではありませんが、《鈴木大拙館》については生成AIで良く引用されているので、また、本ブログでは無償で情報提供する個人サイトに属すると判断してここに置きました。論争が多いテーマほど長くなる傾向があるWikipediaですが、本件は(英語は更に)とてもシンプルで、上記の他サイトの傾向をそのまま反映しています。👉引用は日本語サイトから。英語は(R5年現在)殆ど中身がありませんので。当然リンクで〈鈴木大拙〉その人に飛べば、(いつも通り饒舌な程)沢山のエピソードは得られます。
御礼🔶あとがき
🔶最後までご覧いただき、誠にありがとうございました! 本ブログに関するご意見やご要望がございましたら、メニューの📧Assistance & Services📞よりお気軽にお声がけください。🔶Gold(v.3a.0a.1a/S1)