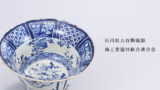本ブログは観光業、企業接待、留学生対応等で英語案内が必要ながら、多忙で準備に時間をかけられない方々の為にすぐに使える情報を分かりやすく解説しています。今回は『どうする英語案内?AIを超える為の情報支援』シリーズの《九谷焼》編です。
0- 基本的な考え方
本シリーズでは《九谷焼》に関する代表的な情報サイトを(A)目的と(B)カバー範囲に照らして下記の5領域『政府(①国外展開、②国内展開)系、③自治体・公益系、④協業(専業者)系、⑤独立系』に分けて(一例として)ご紹介しています。この(A)(B)視点により現場の皆様が自ら日々検索される膨大な情報に(AIにはできない)より深堀した判断が加えられます。👉5領域分類の背景についてご参照の際は《Info@ブログついて》へ。
1.政府(海外展開)系
ここで引用したサイトは(A)目的は国際競争、(B)カバー範囲は世界規模として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。
Travel Japan(JINTO:日本政府観光局)【多言語】
ここでは、政府公式サイトとして、全世界に何をどの様に発信(表現)しているかチェックできます。海外の観光事業者や個人インバウンドは基本的に知っている情報と想定して案内内容を整理する事ができます。今回テーマの《九谷焼》を「kutani」でサイト内検索頂ければ、インバウンドの関心を引くための(1ページほどの)コンテンツと英語表現が確認できます。👉下記引用(R5年掲載記事)は’Fashion Authentic Kutani’からです。今回は窯跡展示館をネタにしてますが、オフィシャルサイトとの(商品ビジネスとしての)紹介の視点の違いも参考になります。
Japan Guide【英】
正式な政府機関ではありませんが、政府認定資格のVisit Japan 大使が設立した訪日観光情報サイトで、特に欧米系の利用者が多く、海外発信力の強さからこのグループに置いています。生成AIもよく引用していますが、(R5年現在)《九谷焼》に関しては陶器のカテゴリーで有田焼と並べて紹介されています。歴史的背景も含めて当然ながら日本の陶器の特徴を興味を唆る様に書かれていますが、この中に入れて貰えるのはジャポニズム以来の知名度でしょうか。👉下記引用は’Japanese Pottery’からです。細かいですが、このバリバリのネイティブサイトでも、日本でよく使われる、陶磁器:ceramics、陶器: pottery、磁器: porcelainの定義と異なるので、改めてユニバーサルな対訳がないこと確認できます。
Highlighting Japan
日本文化発信を目的にした政府広報なので即効性のある情報収集でなく、富裕層対応の為のネタ蓄積に有用です。基本的には外人ライターによるものなので、夫々の視点、内容、表現は参考になります。👉下記引用はちょっと古いてすが《九谷焼》記事です。’Kutani’や工芸品ワードで検索すれば、その他のバックナンバーからも関連記事ありますが、その辺りはお好みで。
2.政府(国内展開)系
ここで引用したサイトは(A)目的は国内活性、(B)カバー範囲は国内規模として発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。
地域観光資源多言語解説文データベース【日英】
適切な観光案内英語表現教育目的のDBなので、今回も一通りチェックしました。特に《九谷焼》は歴史的な経緯から美術館や窯跡が散らばっていて多いので、全国レベルで何が定義されているか確認できます。ただ、DBの更新は長年されていないようなので(この世界は常に新しい発掘発見で状況が変わるので)現在は変わっているかもしれません。《九谷焼》では[九谷焼美術館][伝統工芸][九谷焼窯跡展示館]が(短い記事ですが)検索されます。まず挙げられるのはこの2カ所かですね。👉下記引用は[九谷焼窯跡展示館]です。
伝統的工芸品産業振興協会【日】
英語案内自体に役立つ内容はあまり得られませんが、ビジネス絡みの対応(海外バイヤー招聘等)で使える要素はあります。経済産業省系の一般財団法人として、陶磁器工芸品の保護育成に係る支援していますので、《九谷焼》の位置付けを確認できます。単に利点だけを訴えるセールスピッチでなく、《九谷焼》を含む伝統工芸品の歴史的課題も認識しておくと、共感に繋がり易い幅の広い商品紹介に繋がります。👉下記引用はポータルサイトです。
ポータルサイト:a) 伝統的工芸品産業振興協会 (kougeihin.jp)
伝統工芸 青山スクエア【日】
上記の伝統的工芸品産業振興協会が運営するギャラリー&ショップで、[工芸品を知る]から競合陶磁器、他種食器の全国の店舗が参照できます。その他では[外部催事]からイベント情報チエックができますが、何より、ローカルでの《九谷焼》状況だけでなく東京エリアでの動きを把握しておくと、業界関係者とのやり取りに便利です。👉下記引用はポータルサイトです。
ポータルサイト:a)伝統工芸 青山スクエア (kougeihin.jp)
国立工芸館【日】【英】
日本唯一の工芸専門美術館として国内外に情報発信していますが、その中でも《九谷焼》は前田藩の産業振興策や明治政府の外貨獲得アイテムであった歴史から、現在も伝統工芸頻出の中でも特別なアイテムでもあります。関係展示の際は最大限活用したいですね。(2020年に石川県金沢市に移転)
3.自治体・公益(地域連携)系
ここで引用したサイトは(A)目的は地域活性、(B)カバー範囲は自治体規模として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。
石川県立伝統産業工芸館
金沢市内での《九谷焼》に係るインバウンド対応(展示、デモ、体験)チェックに使えます。立地の良さを活かし、移動時間のないインバウンドへ(定期的な他の工芸品と順繰りに)実演デモも使えます。
能美市九谷焼美術館【多言語】
名前の通り、能美市の公的施設として主に海外への情報発信とインバウンド(観光だけでなくビジネス目的の訪日外国人)への(体験含めた)啓蒙に活用できます。ホームページは多言語対応されてますが、既にサービス終了した組み込みGoogle翻訳のようですので英訳内容はご参考程度で。
石川県九谷焼美術館
加賀市大聖寺駅近くにあるので、急な導線変更に活用できます。2階はフリーで入れますが、《九谷焼》で様々な飲み物が楽しめます。ホームページは厳密な対訳ではありませんが多言語対応含め、詳細に記載されています。上記美術館と同様の活用が可能です。
Kutaniyaki Art Museum Official Web Site
九谷焼窯跡展示館
こちらは貴重な国指定史跡として、加賀地区観光コース向けですが、海外バイヤーの啓もうにも使ええます。(下記引用は正しくありません。訂正まで少々お待ち下さい。)
加賀市役所【多言語】
地元が生んだ2大伝統工芸品《九谷焼》《山中漆器》は観光業、地場産業の竜面で随所に散見できます。必要に合わせて一度チェックされることをお勧めします。👉下記引用は日本語ポータルです。
九谷焼解説ボランティア
4.協業組織(専業者)系
ここで引用したサイトは(A)目的は直接収益、(B)カバー範囲は地場産業として置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。直接的にインバウンドからマネタイズするビジネスモデルと言えます。観光だけなくビジネス系のインバウンド対応にも使えるコンテンツが多いので、その用途では重要チェックグループです。《九谷焼》は一旦中断した後、様々な窯が発展的に分派した歴史からいくつかの組合に分かれていますので、目的に合わせた活用が必要です。👉工房見学については皆様お得意のお好みキーワードで検索して直接予約てきますが、下記のいずれかの組織が関わっていること念頭に置いていただければ、ビジネス商談を絡める際にお役に立つと思います。著名な工房だけでなくこれだけの方々が様々な営業活動をされています。
石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会【日】
九谷焼産地の6組合(能美市☓3+ 加賀市☓1 +小松市☓1 +金沢市☓1)から成り、能美市の拠点で大括りでの九谷焼ブランドの管理、育成、企画、プロモーション活動を主務としています。観光案内に直接関わる前線組織ではありませんが、《九谷焼》に係る諸対応(特に販売ビジネス)はここで管理されていますので、組織の存在と役割だけご認識下さい。
石川県陶磁器商工業協同組合
(略称!商業組合):連合会(6組合)メンバー。能美市に拠点を置く卸、商社グループで(現在のところ)66の組合員で構成されています。下記引用はポータルからで、組合員リストや販売サイトから国内外への発信状況が把握できます。こちらもビジネス絡みの対応に活用できます。👉主な組織的な関連サイトとして[九谷焼協同組合][九谷焼彩匠会:11社製造販売組織][九谷陶芸村][九谷焼団地協同組合]があります。
加賀九谷陶磁器協同組合
(略称!加賀久谷):連合会(6組合)メンバー。九谷焼発祥の地(本組合の拠点は加賀市山代温泉)として、少数精鋭で個性的な作風とその精神性の伝承、並びに組織としての(当然[オンライン販売ショップ]も取り込んで)独自性の継続を目指すグループです。👉主な引用サイトとして[九谷焼について]での、インバウンドが好むストーリー作りから[作家紹介]での、最新企画まで、英語案内ネタに活用できます。
石川県の西端、福井県との県境にある加賀市。古くは江沼郡と呼ばれ、加賀前田家の支藩、大聖寺藩十万石の領地であったこの地が、私ども加賀九谷陶磁器協同組合の”ホーム”です。
九谷焼協同組合
本組合自体は連合会(6組合)メンバーには入らないようですが、能美市に拠点を置き(現在のところ)39の組合員で構成されています。殆どは前述の商業組合メンバーですが、メンバーでない商社もあります。👉メモ[JAPAN KUTANI]デジタル総合カタログは海外展開ツールとして(工芸品の海外バイヤーには)オススメです。
現代生活にむけた新しい商品と本物の石川県の九谷焼の良さを発信、販売しています。
九谷焼窯元工業協同組合
(略称!窯元組合):連合会(6組合)メンバー。歴史的に分業化が徹底修練されている伝統工芸品製作を、ここでは《九谷焼》の材料陶石から完成品までの全工程の展示施設として、小松市に拠点を置き体験工房やオンラインショップ(CERABO)を展開しています。ここもヘビーな工芸品愛好家、有田焼、九谷焼の陶器愛好家の案内に活用できます。
CERABO KUTANI/九谷セラミック・ラボラトリー | 窯元組合
九谷上絵協同組合
(略称!上絵組合):連合会(6組合)メンバー。文字通り上絵技術の研究継承に注力(能美市拠点/R5現在54名所属)。同サイト[販売部]で上絵視点(円&ドル表示)プロモーションもされています。《九谷焼》は上絵!と思っている海外愛好家、バイヤーにはオススメかもです。
金沢九谷振興協同組合
(略称!金沢九谷組合):連合会(6組合)メンバー。《九谷焼》の発展的分派の歴史を物語る、作家と販売店からなる金沢市に拠点を置く(R5現在24名所属)組織です。金沢立地の(近場の)利点が活用できます。
5.独立組織(産業別)系
ここで引用したサイトは(A)目的は間接収益、(B)カバー範囲はイベント&プロモーションとして置いてますので、発信内容(表現)も発信規模もそれを反映しています。上記4系統以外では得られない、独自ノウハウや経験をベースに個性的に展開されているサイト数多(旅行事業、地元個人ベースサイト等)ありますが、冒頭の主旨からも、ここでは細かな引用は控えます。(観光業、販売業に係る皆様はもちろんこのグループはよく熟知されてますので)代表事例として下記ご紹介致します。
山中温泉
殆どの方には引用するまでもないですが、観光案内であれば(英語表現は得られませんが)ここのチェックは必須なので念のため。[R5年現在]体験のくくりで紹介されています。
KOGEI JAPAN
国内に数多ある伝統工芸品に特化した販売事業者はそれぞれ自社サイトにわかりやすい商品説明を展開していますが、その事例として下記引用します。上記『4.専業者』が製作者の表現であるのに対し、これは販売者の表現なので、バイヤーにとってよりわかり易いと言えます。それでも専門的な用語は多く、英語案内者はそれを更に口頭に再編成しなければなりませんが、ネタとしては有用です。👉下記引用は《九谷焼》英語パートです。
御礼🔶あとがき
お忙しい中、今回も最後までご覧いただき大変ありがとうございました。今回テーマだけでなく本ブログは今後も定期的にブラッシュアップして参りますので、引き続きご参照のほど宜しくお願い致します。🔶Gold(v.3a.0a.1a)